2024.2.21 稲山正弘教授特別講演会のご報告
2024年2月21日に茨城県取手市にあるICI総合センター内W-ANNEXで、東京大学大学院 稲山正弘教授特別講演会を開催しました。オンラインで250名以上の一般の方々にもご参加いただきました。
第Ⅰ部では稲山先生が前田建設と共に作り上げた施工事例を、当時の記憶や手書きの構造計算書をふんだんに盛り込んだ資料でご説明いただきました。3月の大学の最終講義は技術的な話が主になるため、木造建築作品は「本講演会が最終講義」の気持ちで用意されたとのことです。

稲山先生が前田建設と初めて共に仕事をしたのは住田庁新庁舎で、外観の特徴的な木の格子は、光と風を通す耐力壁です。大槌町文化交流センターおしゃっちは復興のシンボルとして建設され、連続2段方杖門型アーチ架構(立面)、立体張弦トラス架構(多目的ホール)、木造大スパン樹状方杖架構(図書館)と3つの特徴的な木造架構を合理的に採用されたそうです。他、桐朋学園音楽大学木造4階建校舎、国際基督教大学A体育館、などの物件を稲山先生の目線で説明されました。
稲山先生が講演会の中で何度か繰り返されたことがふたつあります。ひとつめは、軒の出が深い木造は外壁の傷みを抑えることができるので望ましいということ。ふたつめは、木造設計者のポリシーとして、木造は特殊なサイズの木材を使うのではなく、住宅規格の木材のサイズと特殊金物使わずにできる事を目指しているとのことです。理由は業者参入の壁を低くするためと、コストを抑えるためです。
また、がんばって木造で設計しても耐火の必要性から、構造体現しにできない物件を残念に思う事もあり、「次つくる時は、(木の)構造体現しにしたいね」と建築家の隈研吾さんと話をしたとお話をされました。
第Ⅰ部の最後は、前田建設と共同開発した「木鋼組子®」についてです。高層建築物に使用する目的で開発し、水平力を負担するものです。これの良い点は木の構造体が現しにでき、光と風を通せるようになっているところで、今後の使用が期待されるとのこと。以上で第Ⅰ部は終了になりました。
第Ⅱ部は、稲山先生と首都大学東京(現 東京都立大学)名誉教授 深尾精一先生との対談で、深尾先生が実際に見てきた稲山先生の作品13点を深尾先生撮影の写真で振り返りつつ、これからの木造についてのヒントもちりばめて、語っていただきました。
深尾先生が用意した稲山先生設計の物件紹介は、1998年竣工のいわむらかずお絵本の丘美術館から始まりました。岐阜県立森林文化アカデミー、日光金谷ホテルの補強、群馬県立松井田町立九十九小学校、稲山先生の自邸、東京大学弥生講堂アネックス、オガールプラザ、2020年竣工の飯能商工会議所まで様々な用途、様々な意匠設計者との協業によるものです。
各物件に対し深尾先生が、これは素晴らしい!だったり、もはや(構造設計者ではなく)意匠設計者の稲山正弘だ!と褒め、逆に「これはやりすぎじゃないかと思う」など本音も飛び出しました。片持ち屋根の予定が、事業主の意向で安全性向上目的の鉄骨梁をいれた物件は、「(深尾先生)今でも悔しいのでは?」「(稲山先生)悔しいです。」と、構造設計者同士ならではの気持ちを共有されました。
全体を通じて、意匠設計者の違いによって、構造設計者稲山先生の見せ方が大きく異なることを、写真元に説明いただきました。また、日本三名橋のひとつ錦帯橋を例にだされ、錦帯橋は木の橋だが金属の金物や石も使われており、木造といえども闇雲に木を使う事が正しいという考えではなく、適材適所が望ましいというご意見でお2人同意されました。
残念ながら、ここで時間切れになってしまいましたが、木造の今後を考えると、コストの話も重要で、なぜなら中止になったものの多くはコストが合わなくてだめになってしまったからだとのことです。その話は次回持ち越しとなりました。
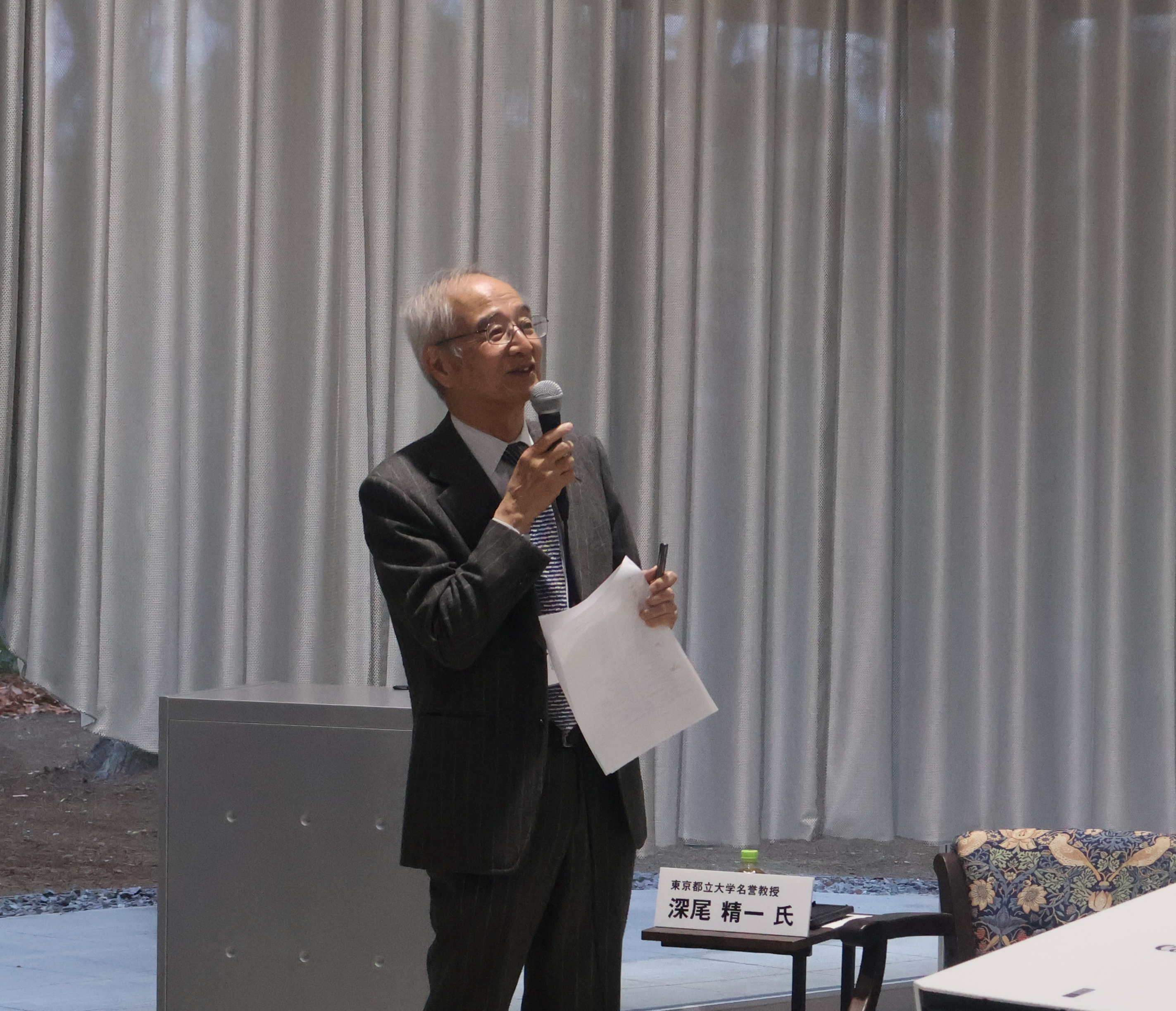
その後の立ち話で、20代の前田建設社員から「勝ち逃げは許しませんよ」と言われた稲山先生、ぜひ退官されて以降も木造建築をリードし続けてください!
2時間という長丁場のはずが、あっという間の時間でした。今回の講演会も多くの方にご参加いただき、盛況のうちに終了することができました。ご参加いただきました皆様も改めてありがとうございました。ご興味のある方は、今後も様々な講演会を継続して開催してまいりますので、ぜひお申込みください。